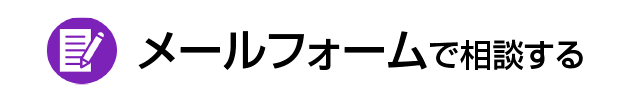あなたの会社にウェブサイトがあるなら「障害者差別解消法」と「ウェブアクセシビリティ」について把握しておこう

2024年4月より、「改正障害者差別解消法」が施行されました……と言われても、多くの方には馴染みがないかもしれません。「障害者差別解消法ってなに?」という方がほとんどかもしれません。でも、もしあなたの会社がウェブサイトをお持ちであれば、必ず知っておかなければならない法律と言えるでしょう。
障害者差別解消法とは、読んで字のごとく「障害者の差別を解消するための法律」。正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」だそうです。内閣府が発行するリーフレットを見ると一目瞭然ですが、結論から言えば「施設や店舗、自治体、企業などが、障害のある方から対応を求められた時に、対応に努めてください」ということです。例えば、音が聞こえづらい方に筆談を求められた時や、目の不自由な方に音声での対応や店舗の床面のレイアウト(つまづきやすいところに障害物があるなど)への要望があったときなどに、できるだけ対応しましょう、などなど。
障害者差別解消法は2013年に制定され、2016年に施行されましたが、上記のような対応(「合理的配慮の提供」と呼ばれています)は「努力義務」となっていました。つまり、「配慮するように努めてね」ということです。新型コロナワクチンの接種が「努力義務」でしたので、つまり「やらなかったからといって罰則があるわけではない」のです。
しかし、障害者差別解消法はその後、2021年に改正されました。この「合理的配慮の提供」が、「努力義務」から「義務」へと変わりました。つまり「かならず配慮してください」「やらなかったら罰則もある」法律になったというわけです。
こちらに関しても内閣府のリーフレットが詳しいので、そちらを読めばご理解いただけると思いますが、押さえておくべき点は、「対応は必須だけど、要求を全て飲まなければならないというものではない」ということです。施設や店舗側にも、極端に言えば建屋を作り替えないと対応できないような要望もあるかも知れません。そんな時に、「無理です」と突っぱねて終わりにするのではなく、相手との対話の中でお互いに歩み寄る姿勢が求められます。要するに、施設や店舗側の都合で障害のある方を門前払いするようなことがまかり通っていたので、「これはなんとかしないといけない」となって生まれた法律なんだと思います。
障害者差別解消法は、障害のある方が、そうでない方と同じようにサービスや情報を得られることが目的ですので、実際の施設や店舗にとどまらず、当然ウェブサイトでも対応が必要です。
例えば、あなたの会社のウェブサイトは、目の不自由な方が音声読み上げソフトで閲覧しても、問題なく情報を得られるように作られているでしょうか。色覚特性のある方が見えなくなってしまうような配色はされていないでしょうか。先に書いたように、全てを解消しておかなければ罰則があるということではなく、訪問者から求められた時に、対応する姿勢ができているかが大切です。
すでにウェブサイトのエンジニアやマーケター向けのメディアでは、ウェブサイトのアクセシビリティ(誰でも使いやすいサイトになっているか)についての取り組みの現状やTipsなどが多数発信されています。取り組みの状況は、わたしたちも含めて、まだまだこれからという感じではありますが、企業であれば顧客から、エンジニアであればクライアントから、今後問い合わせが増えてくるに違いありません。ウェブアクセシビリティについて調べ、施策を実践するにおいて、今が速すぎるということはないでしょう。
また、一部では「ウェブアクセシビリティが義務化された」と誤解されている方もいますが、先に書いた通り、義務化されたのは「障害者への配慮」であって、「ウェブアクセシビリティ」自体が義務化されたわけではありません。ウェブサイトにおいて「障害者への配慮」を行う場合、「ウェブアクセシビリティ」を意識する必要が出てきますよ、という意味ですし、そもそも「ウェブアクセシビリティ」とは、決まった形のあるものではなく、障害者を含めたみなさんが使いやすいウェブサイトであれば、それで良いのです。
当社では、ウェブアクセシビリティを改善するためのツール「WATSON AI」をご提案しています。低コストで手間なく改善でき、継続的なアクセシビリティの向上が可能です。無料でサイトのアクセシビリティを診断するサービスも行っておりますので、「ウェブアクセシビリティは対応していきたいけど、技術もコストもあまりかけられないし……」という方は、ぜひ一度、当社のサービス紹介ページをご覧ください。下記のLINEやメールフォームでも、ご相談を受付中です。
*WATSON AIは、バナナラボ合同会社が提供するウェブサービスです。